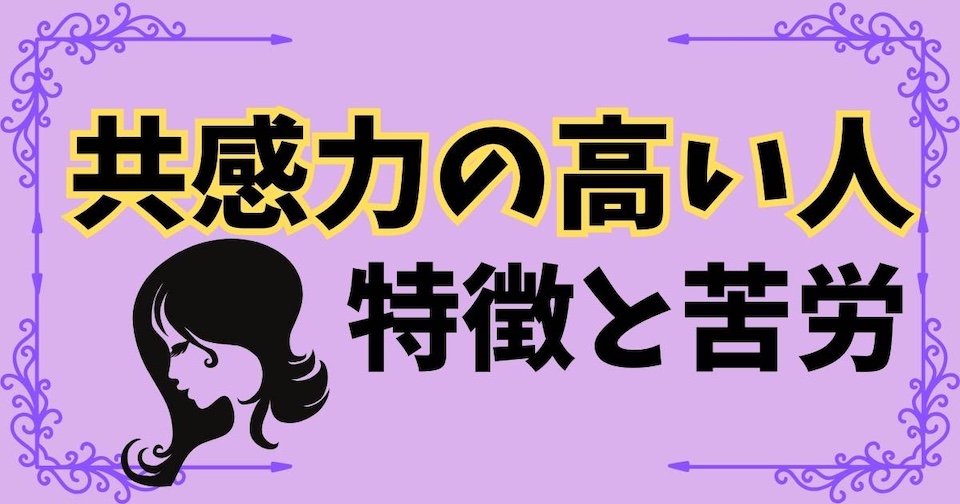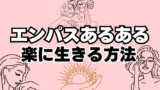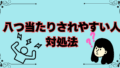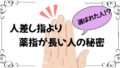「人の隠れた気持ちにすぐ気づいてしまう」
「場の空気が読めすぎて、ぐったり・・・」
「あー、今日も共感疲労がつらいわ・・・」
あなたは、もしかしてこんな風に感じる共感力の高い人でしょうか?
共感力が高い人は人の感情や場の空気が非常によくわかるため、上手に人間関係に作れたり、人に信頼されやすいとう長所があります。
しかし一方で、あまり理解されない独特な苦労を背負うことも多いのです。
今回は、共感力が高い人の特徴と人生における苦労について紐解いていきます。
共感能力が高いとつらい理由、共感力が高い人がその力を活かして、幸せに飛躍する方法を解説しましょう。
リアルな人生体験を元に心理学的に、そしてスピリチュアル視点も入れての考察をお届けします。
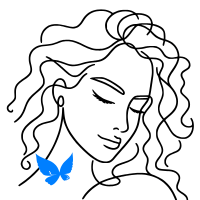
どちらかというと「共感力が高すぎる人」の
記事になるかもしれません
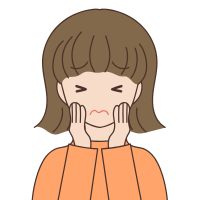
エンパスは共感能力が高すぎる人ですっ
- 共感能力とはいったい何?
- 共感力が高い人の特徴
- 共感力が高い人は人知れず苦労が多い
- 共感力が高い人をスピリチュアル的に見ると?
- 共感力が高い人の対処法
共感能力とは何か?

共感能力とは、他人の感情や状況を感覚で理解し、まるで自分のことのように感じ取る力です。
「空気を読む」といったレベルを超えて、相手の内面の痛みや喜びの感情を強く感じ取るのが特徴です。
ミラーニューロンと共感の仕組み
神経科学では「ミラーニューロン」という脳の働きが共感能力に関わっていることが知られています。
相手の表情や仕草を見ただけで、その人の感情を自分の中に再現してしまう神経細胞です。
例えば、誰かが痛そうに足をぶつけるのを見て、自分も「イタッ」と感じる。
怪我をしている人の映像を見て「ううっ」と血の気が引く。
これはまさにミラーニューロンが働いているからです。
共感力が高い人とは、ミラーニューロンの働きが過剰な人とも言えるのです。
逆に共感能力が低い人は、ミラーニューロンの働きが弱い人ということですね。
共感力が高い人の特徴
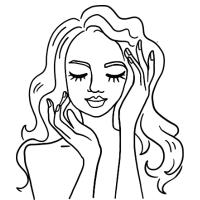
共感力が高い人には、興味深い特徴があります。
心理学的に見る共感力が高い人の特徴
- 人の表情や声のトーンに敏感で、ちょっとした変化もすぐ察知する
- 相手の感情を 自分のことのように感じ取る
- 相手の悩みや不安を聞いた後に、自分までどっと疲れてしまう
- 他人の気分に左右されやすく、 場の空気に同調してしまう
- 自分よりも他人を優先し、 自己犠牲的になりやすい
- 「NO」が言いにくく、頼まれると断れない
- 他人から相談されやすく、「話すと安心する人」と思われる
- 周囲から「優しい人」「気が利く人」と評価されやすい
共感力が高い人は「人の心にすぐ気づき、つい自分よりも相手を優先しがちな人」です。
この特徴は、優しさとして現れる大きな魅力で、人を安心させる力でもあります。
ただ、気づけば疲れていたり、「どうして私ばかり…」と感じてしまうこともあるかもしれません。
共感能力は素晴らしい才能ですが、そのままでは自分をすり減らしてしまうという課題がつきものなのです。
スピリチュアル視点で見る共感力が高い人の特徴
- 周囲の波動やエネルギーを自然に感じ取ってしまう
- 人混みや雑踏などでさまざまなエネルギーを拾ってしまうので疲れやすい
- 初対面の相手でも「この人は信頼できる」「この人は危ない」と直感的にわかる
- 人の心を開きやすく 相手が本音や感情をこぼしてしまう ことが多い
- 他人のネガティブを吸収しやすく気づけば感情が重くなっている
スピリチュアルな視点で見ると、共感力が高い人は目に見えない波動やエネルギーに敏感なアンテナを持つ人だといえます。
周囲の空気を読むだけでなく、直感的に人や場所の本質を感じ取る力があるため、安心感を与える存在になりやすいです。
ただし、その感受性の高さゆえに、人混みで疲れやすかったり、他人のネガティブを抱え込んでしまうこともあります。
つまり、光を受け取りやすい分、影も吸収しやすい。
そんな両面を持っているのです。
共通して見られる行動パターン
- 争いを避ける傾向があり、 反論せず我慢してしまう
- 誰かが不機嫌だと「自分のせいでは?」と考えがち
- 人から八つ当たりされやすい(安全で受け止めてくれる人に見られる)
- 「自分の気持ち」と「他人の気持ち」の区別がつきにくい
- 気を使いすぎて、人間関係で 心身ともに疲弊 しやすい
これらを見ていくと、共感力が高い人は「人との衝突を避け、つい自分を後回しにしてしまう人」だとわかります。
誰かの機嫌が悪いと「私のせい?」なんて考えてしまったり、人の感情の受け皿を引き受けてしまうのですね。
その結果、いつの間にか「自分の気持ち」と「他人の気持ち」が入り混じり、疲れ果ててしまうこともあります。
本来は優しさゆえの性質ですが、無理を重ねれば心身に負担となってしまうのです。
だからこそ、相手を大切にするのと同じくらい、自分自身を守ることも大切で、それが、共感力という素晴らしい力を使いこなすための鍵となります。
生育環境や心理的背景

共感能力の高さは、必ずしも生まれつきではなく、その能力を磨かざるをえなかった背景があることも実は多いのです。
たとえば、幼少期に家族に問題のある人がいたり、機能不全家族のもとで育った場合に、その環境で生き延びるために共感能力を強化してきたというケース。
不安定な親の機嫌を読まざるをえなかったり、家族のために敏感に空気を読んで、誰かを癒す役目を背負ってきたケースもあります。
このような幼少期の経験が人格形成に大きな影響を与え、大人になっても瞬時に人の感情を察知して、調整する(癒そうとする)役割をする癖が染み付いていることも。
幼少期にサバイバル能力として身につけた高い共感能力は、多くの場合、大人になってから自分を苦しめる原因になります。
ついつい人の感情の面倒を見てしまったり、自動的に人の気持ちを癒やそうとしてしまったり、他者の課題を背負ってしまったり・・・
こうした人の境界線を越えた行動は、問題のある人や甘えた人を呼び寄せます。
共感力が高い人は、厄介な人のターゲットとなり、際限なく当たり前に無償の奉仕を望まれ疲弊することがあります。
共感力が高い人の苦労

共感力が高いのは素晴らしいことですが、一方、大きな負担にもなります。
共感疲労を起こしやすい
他者の気持ちを自分のことのように感じて、苦しくなることがあります。
相談を受けたあとにどっと疲れてしまうのはこのためです。
しかし「共感力が高い人」は全体から見て少数派ですから、周囲にはなかなか理解されません。
自分が抱えたものを解放したいと思っても同じレベルで、感情労働ができる人はそれほどいないでしょう。
また、人の負の感情の重さをよく理解しているので、自分に悩みがあったとしてもそれを簡単に誰かに相談をすることに罪悪感を持ちます。
結果的にさまざまなものを抱えやすくなります。
八つ当たりされやすい・感謝されない
共感力が高い人は、無意識のうちに相手の感情を解放させてしまう特徴があります。
人は自分の話を寄り添って聞いてくれて、かつ反応してくれる人に心を開きますから、共感力が高い人は当然「すごく受け止めてくれる人」と認識されます。
さらに、この人には何を話してもいい、何をしてもいいというエスカレートした思いにさせてしまうことがあります。
もちろん、無意識レベルでの作用となりますが。
共感力が高い人は人の心のストッパーを自然に外してしまうのですね。
これが行き過ぎると、高い共感性という特性はマイナスに作用し、他者のエネルギーを欲しがるエネルギーバンパイのような人を引き寄せたり、八つ当たりしたい人のターゲットになります。
人の感情に寄り添うことがあまりにも自然であると、その弊害もあるということです。
そして、哀しいことに、人の悩みや愚痴を聞くという感情労働を日常的にしすぎていると、それが当たり前になり感謝さえされなくなるという現象が起こります。
関連記事:八つ当たりされやすい人の特徴と対処法
関連記事:エネルギーバンパイア
期待されすぎる
共感力が高い人は、相手の望むものが大体わかります。
相手のかけてほしい言葉も透けて見えます。
察してほしいような言葉を言ってくる察してちゃんや「匂わせ」発言をする人にはちょろい奴だとと思われて、狙われます。
共感力が高い人は「この人、嘘っぽいな」と思いながらも察してちゃんや匂わせちゃんのその裏にある寂しさに気づいてしまい、結果的に相手のお望みに答えてしまいモヤモヤすることもありますね。
「あなたならわかってくれる」と頼られやすく、必要以上に人の問題を抱え込んでしまうことも共感力が高い人の「あるある」です。
ちなみに、過剰に人に期待をしてくる人は、自分の思い描いた理想と相手が違ったときに、ひどくこき下ろすのがデフォルトですので注意が必要です。
自分の気持ちがわからなくなる
人に寄り添いすぎるあまり、「これは自分の感情?相手の感情?」と混乱してしまうこともあります。
自分の気持ちを後回しにして(あるいは無にして)人に尽くすことが癖になっていると、その後の人生で要らぬ困難を呼び寄せます。
共感=同意と誤解される
共感力が高い人は、その共感が同意であると、誤解されることがしばしばあります。
「共感する」と言うのは、「あなたの感情がわかるよ」という意味であって、必ずしも「私もそう感じる!そう思う!」ではないのです。
しかし、共感=同意と勘違いしてしまう人がいます。
特に共感能力が低い人ほど、共感=同意と勘違いしやすい印象です。
さらなる勘違いで共感してくれた相手を自分と同一視してしまうケースもあるので、共感力が高い人は、認識がずれている人に巻き込まれないことが大切です。
「あなたの気持ちはわかるが私はあなたではない」
共感力が高いことは決してマイナスではありませんが、人間関係において脆弱性として働き、意図せず狙われる結果になることがあります。
人間関係の境界線が曖昧な人に対しては、心して健全な境界線を引くことを心がけましょう。
共感力が高い人が自分を守る3つの方法

共感力が高い人の特徴を集約するとこのようになります。
- 感受性の強さ
- 境界線の薄さ
- 他人を優先する傾向
これは弱点ではなく「貴重なギフト」ですが、そのままでは人生の苦労も増えていきます。
共感力が高い人が共感能力を上手に活用して人生を輝かせるためには、自分自身を適切に守ることが大切です。
健全な境界線を引く
「これは相手の問題」「これは自分の気持ち」などと線を引くことが大切です。
全部を背負わなくてもいいと自分に許可を出しましょう。
長年、家族の問題や周囲の人の問題を自分ごとのように背負ってきた人にとっては、なかなか難しいことことかもしれません。
そして境界線の引き直しにより、周囲がまるでホメオスタシスのような役割をして、あなたを引きもどすこともあるでしょう。
しかし、自分の課題は自分の課題、人の課題は人の課題というように論理的に考えていくことが、自分を守り、さらには人間関係を良好にすることにつながるのです。
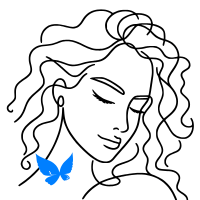
境界線を引くのは冷たいことではないんですよ
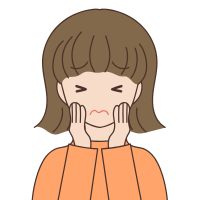
境界線!学校で教えて欲しかった!
自分だけの時間を持つ
共感力が高い人は人に囲まれる時間が長すぎると、心が疲弊します。
決して人が苦手だとか、コミュニケーションが苦手というわけではないので理解がされづらいことですが。
心が疲弊する理由をわかりやすく言うと、人の感情や場のエネルギーをキャッチしすぎて情報過多になり、尚且つ処理能力オーバーになるというところでしょうか。
また、人の感情などの微細な情報を掴む人間だと認識されると、その通訳者として求められることも多くなり疲れてしまいます。
例えば・・・
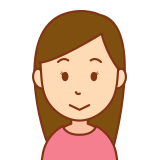
あの人どう思っているかな?教えて!教えて!
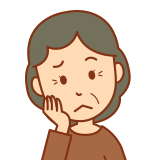
心配だわ、大丈夫かしら?あなたどう思う?
共感力が高い人は、気働きや感情労働を必要以上にやってしまいがちで、実は意外と見えない仕事を自ら多く引き受けてしまうことも「あるある」です。
一人で過ごす時間や自然の中でリセットする時間を大切にして、「見えない」仕事を休んでください。
共感を選んで使う
誰にでも共感する必要はありません。
こう言うと、息をするように人に共感して生きてきた共感力の高い人は驚くかも知れませんが、多くの人たちは人を選んで共感し、人を選んで優しくしているのです。
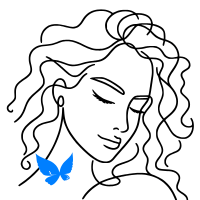
これを知った時は驚きでした!
誰彼構わず、自分のエネルギーを使うことはしていないのです!!
普通の人は感情労働であまり疲弊しません。
むしろ、人に共感すると言う概念が希薄でいつも自分のことばかり、いつも自分の感情でいっぱいというような人も増えています。
人の気持ちなんてわからないから、ないのと同じと思っている人も一定数存在します。
これを理解しておきましょう。
共感力が高い人は「この人には力を注いでもいい」「この人には距離を置く」と、意識的に優しさを使う相手を選びましょう。
関連記事
共感力が高い人をスピリチュアル的に見る

心理学的には「共感力が高い人」と説明されますが、スピリチュアル的に見ると、それは魂が持って生まれた特別なギフトだと考えられています。
波動を感じ取るアンテナ
共感力が高い人は、人よりも繊細なアンテナを持ち、周囲の波動を自然にキャッチしています。
喜びや悲しみ、怒りや不安といった感情のエネルギーは、実は目に見えない周波数のように空間に漂っており、それを感じ取れるのです。
「なんだかこの場は居心地が悪い」
「初めて会ったのに、この人は信頼できる」
そんな直感は、まさにスピリチュアルなセンサーが働いている証です。
鋭い直感によって、人生の折々で危機を察知して免れてきた人も多いはずです。
共感能力を強化してきた背景とカルマ
生育環境の困難さによって、共感能力が強化されているケースがあると解説しました。
もしあなたの共感能力が生き延びるために磨かれた能力であるとしたら・・・・
スピリチュアル的に見ると、高い共感能力を養うためにわざわざ困難のある環境を選んで生まれてきたということになります。
それから、前世のカルマの解消です。
すなわち今生で魂レベルを上げるため、克服すべき困難です。
どちらにしても、必然です。
共通するのは、全てが自分が生まれる前に決めてきたことと言えます。
もしそうだとしたら、共感能力の高さを本当に使うべきことがあると理解できます。
魂の学びとしての共感力
スピリチュアル観点で、共感力の高さは「他者の痛みを知る」という魂の学びとも言われています。
人の感情を深く理解できるからこそ、思いやりや慈愛の心を育てることができる。
そして、その経験の全てが魂の成長につながっていきます。
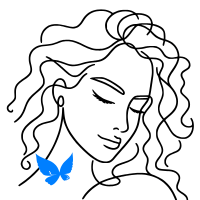
人の痛みはもう十分わかった!
助けて〜お腹いっぱいです
と言いたい共感力が高い人もおられるのではないでしょうか?
無防備な共感はエネルギーを消耗する
一番注意したいのは、無意識にすべての感情を引き受けてしまうことです。
スピリチュアル的な概念においても「不要なエネルギーを抱え込まない」ことが大切だとされています。
つまり、光を分け与える役割をするならば、まず自分自身のエネルギーを守ること。
そうしなければ、他人のネガティブに当てられて疲れ果ててしまいます。
共感能力を上手く活かすと人生が変わる

共感力は「癒す力」や「導く力」に変換できるギフトです。
人の気持ちに寄り添える力を持っていることを自覚して、選択的に意識的に大切に使うと世界が変わります。
共感力が高い人は、自然に仕事をしすぎていて、自分の価値にあまり気づいていないことがあります。
しかし、自己価値に気づいていないと、搾取されるというのがこの世のならいです。
大前提として、共感能力は自分の大事なリソースであり、大きな価値であると自覚しましょう。
価値のあるものをどこにでも誰にでも大盤振る舞いしないように。
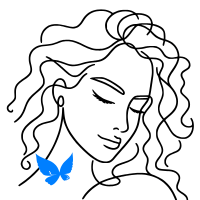
私たちは神ではありませんからw
自分のエネルギーリソースを大切に守って、本当に使いたい時に使いたい人に向けて注ぐと、人生も大きく開けていくでしょう。
- カウンセリングやサポートの仕事に生かす
- 芸術や表現を通じて人を癒す
- 身近な大切な人の心を温める
例えば、このように上手に活かすことで共感力は大きな力になります。
まとめ:共感力が高い人の特徴と苦労
共感力が高い人は、人の気持ちを深く理解できるという大きな才能を持っています。
その一方で、育ってきた環境の影響によって、他人の感情を抱え込みすぎたり、時には八つ当たりの対象になってしまうなど、独特の苦労も背負いやすいのです。
でも大切なのは、この力は「弱点」ではなく「ギフト」だということ。
人を思いやる力は、社会や人間関係においてかけがえのない価値を持っています。
自分を守るためには、まず境界線を引き、自分の時間を持ち、自分の心に寄り添うことが欠かせません。
癖で自動的に共感能力を発動させるのをやめて、意識的に選択的に効果的に使いましょう。
このようなコントロールによって、あなたの共感能力が人との関係をより健やかにし、創造性を伸ばし、人を癒す力としてさらに発揮されます。
今回は共感力の高い人の特徴と苦労について、リアル体験をもとに心理学的に、そしてスピリチュアル視点も交えてお届けしました。
今回の記事があなたのお役立ちになれば幸いです。
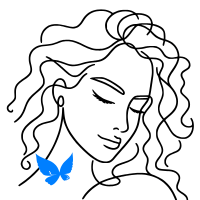
共感力が高いあなたに幸あれ!